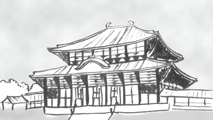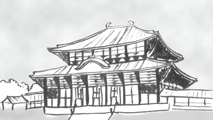今年は東大寺の大仏開眼千二百五十年にあたります。その記念式典が
十月十五日に行われ、ご招待をいただき参加してきました。
東大寺が造られた頃の日本は、国中で乱がおこり、疫病や飢饉が続き、国家の
経済基盤も危うい大変な時期でした。それにもかかわらず聖武天皇は仏教の教えを
広めるために、命がけで大仏造営を遂行しました。インド人の菩提僊那と東大寺の
初代住職の良弁、勧進を行った行基と共に、民衆一人ひとりに訴え、二十六年の
歳月を経て、ようやく大仏はできあがったのです。
なぜそんな大変な時にこんな大事業を決行したのだろうか、と私はいぶかしく
感じました。が、やがて、「いや待てよ、国家が危機的な状況だからこそ、精神の
ありようが大事だと聖武天皇は考えたのではないか、しかし民衆にとっては精神は
見えないもの、それでは分かりにくい、だから求められる精神のありようを象徴する
カタチが必要だと考え、それが大仏様だったのではないか」と思い始めました。
そして、そうした思いを込められて造られた大仏様の開眼の時に、天皇が纏われた
衣が「糞掃衣」(ふんぞうえ)という袈裟でした。「糞掃衣」とは無用になって人々に
捨てられた布を釈迦が拾い集めて縫い合わせた、今でいうパッチワークの布で
できた衣のことです。晴れがましい大仏開眼の日に、聖武天皇が選んだのは、
この「糞掃衣」だったのでした。
今回、その「糞掃衣」が復元されていました。それを見ながら、私はこれはまさに
「命の衣」だと感じ、その尊さに涙が出そうになりました。飽食の時代を経て、
行き詰まり、果てしなく落ちぶれつつある日本の再生の糸口をこの衣に見たような
気がいたしました。
この日の午後二時に銅鑼の音とともに散華が宙から舞い降りてきました。
後で知ったのですが、ちょうどその頃、五人の北朝鮮の拉致被害者を乗せた
飛行機が羽田空港に到着したのでした。
真の平和とは何でしょうか。対立することではなく、説明し、理解しあうこと。
説得した方の人間は、そのことに責任と誠意を持つこと。
天空から舞い落ちてくる散華を見上げながら、自然の教えに従うことの
大切さを思い、すべての生きるものに幸ありますようにと祈りました。
|