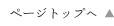店主の
ひとりごと
| 私の京都 |  |
||||
|
「この二十年間」 先代より和服の世界を見せて頂き、それを受け継ぎ、仕事として歩いて二十年。 毎月仕入れやものづくりのために京都に上り、見てきた自分なりの「京の都」に対する想いを、 つれづれなるままに書きたいと思います。 観光として見る時と、仕事を通じて感じる京都では、多少異なった見方になります。 より現実的になることをお許し下さい。 「京の都とは」 仕事を通じ、色々な職方さんや問屋さんの人々と出会いました。 十六代続く問屋さんから二代目の問屋さんまで、色々な格式の違いが感じられます。 さすがに1200年の歴史ある京都らしく代々続いているお店が多い様です。(地方に比べてですが…) 何故京の都に千年以上も都が続いたのかの問いに答える文章を、清水寺貫主大西良慶氏 (百歳の時の著「ゆっくりしいや」)より引用すると、「信心の家は長いこと家が続く、信心のない家は 上がったり下がったり差が大きく短い、信心でも胸に一物を抱いて祈りに参ったはる人は 良い悪いが早う出てくる。この頃顔見せん、参ってこんな、という調子で上り下がりが激しい。 信心は平常心これ道なり。大きなことを思わんと足元を見て進むことや」。 小生はこの文章に京の京たるゆえんを感じるのです。 一言で言えば京都の人々は信心の人々が多いのです。 それが根底にあっていろいろな家が集まり、都が出来上がり、そして千年の都が、結果として 残ったのだと想います。決して山を望まず海を望まず、京には京らしい、静かで美しい心があったから、 先祖代々続く家々がたくさん残り、今があるのです。 歴史的なものの見方で言うと京都の人々はよく、応仁の乱(1467〜1477)のことを指して 前の戦争と言います。応仁の乱は室町時代のことですから、いかに歴史の見方が長いかが 分かります。自然と物事を大きなスパンで考える様になるのかもしれません。 余談ですが、このとき、西軍が本陣を置いたところから「西陣」という名がつけられました。 今も帯屋さんが点在している場所です。
「京の庭」 さて京都の寺院には必ず、そのお寺らしい、美しいお庭があります。 (写真を数枚、どこであるか今回はあえては書きません。次回の文章にてお話します。 写真だけで分かる方は京都をよく知っている通の方です?) そういった庭には人間の、自然に対する感謝と神仏に対する崇拝と、人としてどう生きるかを 自ら考えさせる哲学的な空間を見ることができます。世界中に庭はたくさんありますが、 ただ左右対称でない日本庭園は、その真骨頂だと小生は思います。 よく仕事の合間に訪れては、一人で庭の縁側に座ります。仕事の合間です。 仕事が中心ですので。…すこし言い訳ですが。同じ庭なのに自分の心の高低により違って 見えることがあります。静かに座れば座る程、心が静かになり、色々な事に光がさしてくるのです。 心が整理されてゆくのでしょうか?門より露地に進む、屋敷に入り庭をみる。 この順路に感動するのは小生だけでしょうか。 縁側に座りただ見るー苔、岩、草木—葉の揺らぎに風の存在を知ります。 風は見えない存在ですが確かに感じるのです。そこから空気がなければ生はないなとか… 本当に大切なものは見えないのかとーー回りにある全てが感謝に変わる瞬間、心に涙するのです。 「日常を極めることがお茶の世界です」と教えてくれた人がいます。 そしてそれを心に留めて事物を見ると、日本人は日常をいかに平常心で過ごすかに心をさいた 民族であったかを教えられるのです。 先人達は決して非日常に逃げるのではなく、日常(現実)を見つめてそこに真善美の糸口を見つけ、 それを伝統として私たちに残してくれました。 全ての文化に於いて本歌がある国は世界にもそうないと思います。 そう考えると京の都は本歌の詰まった宝物の地です。
「観光とは」 人が何かを創るとき、そこにはこんなものを創りたいという理想が必ずあります。 これが強く美しいほど、時間を経てまた一段と深く底光りする美しさを持つと、小生は想います。 また、以前、小生のエッセイの中で観光の真の意味は人が光ること、その人々を見に行くことを 観光というそうですと書きました。 今、全て京の都で目にするものは人が創ったものです。人の心が創らせたものです。 その人々の心が真善美の調和の上に創らせた現実を知った上で、いつか、じっくりご自分の 好きな京を散策してみて下さい。 次回は小生の好きな場所や素敵なお店をご紹介します。 室町は着物問屋さんが集っている町です。その中に美味しい御食事処があります。 そんなお話ができればと思います。 店主 |
|||||
| vol.30 (2006年9月発行)より | |||||
| ←back・next→ | |||||