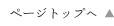|
芭蕉畑と、人と人
蓮井:芭蕉布というと、たいへんな労苦を伴う作業の中で生まれてくる織物で、
日本の織物の中でもとても大きな存在だと思いますが、その作り手として、
今のような世の中をどのように感じていますか?
平良:芭蕉布が、という以前に…、この仕事を続けられるかな、ということをとても考えます。
蓮井:え!それはどのくらい前から?
平良:ここ十年は常に。私達は喜如嘉の芭蕉布の、常に先頭を走ってきたわけだけど、
こんなつらい時代が来るとは思わなかったと感じるくらい…
蓮井:ああそうですか…
平良:芭蕉布は、たくさんの人手と手間をかけてやっと織ることに辿り着けるわけで、
個人のスタンドプレーでは成り立たない。でも、そういう、芭蕉布を支える人達が、
以前とはもう違うんですよ。今は高齢化が進んで、後継者も育てていかなくちゃいけない
わけだけど、ハローワークに募集を出せば、問合せはくるけども、全然違う想いの人達の
集団でしかなくって。若い人は畑仕事なんかやったことないから、なにかやれば救急車呼ぶ
騒ぎになったり。ここ十年間くらい、それまで皆無だった事故がどんどん起きてます。
だから今は、水曜日は芭蕉畑にいかないの。というのは、診療所が休みだから(笑)。
蓮井:共同体が機能しなくなってきているんですね…、
  
みんなの力、一人の力
蓮井:芭蕉布がこの大宜味村に受け継がれてきた理由の一つには、やっぱり、戦後の貧困の
中で皆で力を合わせて復興しよういう意識の強さとか、だからこそ苦労が苦労に
ならなかったというような?
平良:いえ、貧しさの中で、というなら他の産地も残ったはずです。だって沖縄には各地に
その土地の芭蕉布があったんだもの。かつて、山原()、国頭()村、
今帰仁()芭蕉ってもっと有名だったのよ。
品評会やって一等賞取るのは大宜味の芭蕉布じゃなかったの。
首里では、廃藩置県があって氏族の人が副業としてとても良い芭蕉布作ってたの。
それは極上の芭蕉布を。
蓮井:琉球王国の首都ですから技術的にも高度に洗練されてたんでしょうね。
平良:そう、花織りは首里の芭蕉布。他は、田舎の、ど田舎の芭蕉布。それでも村の中で
優秀な選ばれた人だけが技術を習って平織り以外のものを織れた。
確実に、極上の芭蕉布は各地にあったんです。
でもそういう産地になぜ残らなかったかというと、みんなこんなたいへんな仕事を
職業に選ばなかったから。もういいわって、それよりバスガイドになろうって。
当時花形のね(笑)。それから、織物をやろうという若い人に芭蕉布を教える人が
いなかった。戦前にあった工芸学校みたいな場所では、先生は鹿児島や熊本の人で、
沖縄の人がやってないの。そこで教えてたのは絹や麻で芭蕉布を教える人はいなかった。
習わないから、できっこない。
蓮井:だから余計に、芭蕉布を再興するのはたいへんだったんですね。
平良:ええ、田舎のおばあちゃんはみんな芭蕉布を織れたけど、やっぱりそれは商売として
成り立つような、今に生きて行ける芭蕉布ではなかった。そして本当に良い、
極上の、昔の氏族が作ってたようなものは、あっという間になくなってしまった。
だって他に仕事がどんどんあったら、たいへんな仕事はやらないですよね。
蓮井:では何故ここだけに残ったのかというと?
平良:戦後、大宜味村の芭蕉布が残った理由は、平良敏子という存在しかない。
やっぱりひと、人なの。前に進んでリーダーシップを発揮できた人の存在。
蓮井:なるほど…ビジネスに変換しがたい共同体の作業を必要とする芭蕉布制作の中でも、
方向性を示していけるような平良敏子さんの生い立ちや人となりが求心力となり、
それを可能性とした。
時代の潮流に流されず、皆で芭蕉布を織ろう、地域の誇りとして未来に繋ぎ、
発展させていこうとしてきた平良敏子さんの存在があったからこそ、
大宜味の芭蕉布だけが現在まで残り、磨かれてきたのですね…。
これからの美恵子さんのご活躍に期待しています。
どうぞ、大宜味の芭蕉布を子ども達の世代にも守り伝えて下さい。
大宜味村喜如嘉では、一年間に二百反足らずの着物と帯を、二十〜三十人の人たちが
支え合って織っています。本土の圧政や戦禍という激動の歴史の中で伝え残された技を
経糸に、日々の精進を緯糸に、芭蕉布という奇跡に近い織物の物語でした。
|