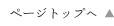対談この人と
話そう...
|
たかす文庫「この人と話そう…」
勝 山 織 物 勝山 健史さん |

|
||||
|
1966年 京都・西陣の機屋に生まれる。
1991年 家業(勝山織物入社) 1992年 洛風林同人として帯製作を始める。 2002年 長野県・飯島町に絹織製作研究所を設立。 |
|||||
| 聞き手 蓮井将宏(や和らぎたかす店主) | |||||
|
【 勝 山 織 物 】
創業1891年。戦後の復興期に、当時の時流とは逆行して「手機で帯を織る」というモノ作りを始め、 以来、今も当時とかわることないモノ作りの姿勢を貫く。 |
|||||
|
■不思議な縁
京都市内から一時間半、左京区京北にある勝山さんの機場を訪ねました。 目的地に近づくにつれ、この辺りに以前来た事があるはずだという気がしてならず…、やはりその感覚は間違いではありませんでした。付近に建つ「山國神社」という神社に以前お参りしたことがあったのです。八世紀末頃創建の厳かな場所で、もう一度お参りしたいと切に願っていた処でした。来るべくしてきた土地だと、心より感謝しました。 |
|||||||
|
■人生は全て決まっているかもしれない、しかし自由である
今回は勝山さんの帯に託す思い、糸に対する考え方などゆっくりゆっくりお聞きしました。 「糸」は陶器においての「土」です。一番大切な土台ですが、糸の風合いを生かすため織りから紋様まで考えて美しい織物を創作している人は限られます。真摯に「糸」を追い求めて来られた勝山さんは、今では古い裂の修復を依頼され、その技術がまた作品に生かされるとも聞きました。それはあたかも古代の遺跡を掘る作業です。そこからまた新たな光(命)が生まれます。 常に変化しつつ、自分らしい自分になろうとしている氏の半世紀の物語です。 飛天錦の帯が出来上がったエピソードもとても楽しいお話でした。
蓮井:勝山さんは「名物裂」の持つ、生地そのものの美しさに魅せられて以来、その風合いに近づくために随分長い間糸を探して来られたそうですが、志村明さんの糸と出会ったのはイタリアのミラノだったということを以前、洛風林の堀江麗子社長から伺いました。全くの偶然だったそうですね。
勝山:その仕立て屋さんで見た洋服地だったので日本の織物だとは思わずに、すごいなイタリア人は、やっぱりすごいもの作らはるんやな、と思いました。
蓮井:探していた時は西陣でも見つけられなかったのに、イタリアで偶然日本の絹を出会うなんて、お釈迦さんの手の中にいるみたいですね。でも、糸は陶芸で言うと「土」。一番大事な部分。現代の織物と「名物裂」と、なにが違うのかというのを追求すると、糸そのものが違う、と。今の機械紡績の糸と昔ながらの糸ではそんなに違いがあるわけですか。
勝山:志村さんの糸やと機(はた)の調整を少ししてやらないと機にかからないんですよ。現在の機は市販の糸に合わせているので。そういう糸に慣れていると、戻すのはたいへんでしたね。織り手さんにも面倒くさいと言われるんですけど、面倒くさい糸しか知らなければそれが当たり前になる。そういう環境ができれば良い。たぶん、繭からひき上がったときの糸というのが一番綺麗なんですよ。後からどんなにいじくるよりも。絹糸本来の美しさをどこか感じるられるようなものに仕上げたいんです。
※志村明 絹本来の美しさを引き出すため理想的な絹糸を追求し、多くの古代裂の復元も多数。 現在、長野にて勝山織物株式会社絹織製作研究所代表、文化財保存修復学会会員 1952年東京生まれ、1975年沖縄県竹富島にて染織を始め、養蚕・糸織り・織りまで一貫して行う。 1993年愛媛県野村町シルク博物館付属織物館 染織講座講師、2003年長野県飯島町へ転居
蓮井:帯は、着物に対してどういう役割だと思いますか?
勝山:アクセントでしょうね。着物も帯もお互いが寄り添うもので、でもあくまでも纏う人が主役。あまり頑張ると着手さんが霞むじゃないですか、僕個人としてはそうであって欲しくなくて。押し付けたくない、というのがすごくあります。選んでもらえるのは幸せな事ですけど、技法と苦労なんかを説明して手にとってもらうっていうのは嫌で、誰が作ったとかじゃなくて、何にも言わずにそこに置いてあるのを気に入った人が求めてもらえたら、それが一番嬉しい。もともと機屋なんていうのは機屋の名前で売るものではなくて、どこどこの帯屋さんのなになにを作る、というものだったので。
蓮井:勝山さんの帯は箔も綺麗ですよね。
勝山:西陣は今ほとんど銀使わないんですけど、酸化して焼けちゃうんで。でも僕は頑なに本銀使ってます。あの柔らかい銀色はプラチナでは出なくて。焼けたら焼けたでそれも良いじゃないかと思って。それよりももし何かあればもう一度作り直せばいいし、これは作り手独特の考え方なのかと思いますが、より良いものを提供すればいいと思っていて。美しいものを美しいまま渡して、使って頂きたいんです。金も本金ですね。
蓮井:古いものの修復もしていているそうですが、そちらはどうですか?
勝山:西陣では知りえないことがどんどん入ってきますね。僕はそれをきちんと資料として残して、次の世代にバトンタッチしていこうと思ってます。
蓮井:でもどうして日本にはそういう古い裂が残ってきたんでしょうね?
勝山:やっぱり裂が好きなんじゃないですか?日本人は。着物として着れなくなると一枚の布キレにして奉納するじゃないですか。残す。使い捨てない。よく日本人は店で了解も得ずにモノを触ると言われますけど、でも、知識で見ようとすると見切れなくて、触って確かめるのが、たぶん正解なんやろうと思うんですよ。そして誰もがその感覚を持っている。
蓮井:最近本で読んだんですけど、日本の伝統は全て医療に繋がるそうなんです。お能、茶道、華道、舞踊。美しいものを見ると精神が整うと言われています。西洋医学とかが入ってくる前から、日本の伝統芸能や技術には人の心を癒す、元気付ける効果があってそれが民衆レベルまで定着している。そういう土壌だからこそ、古いものも大切にされてきたのかなと思うんです。絹は庶民のものではなかったですけど、やっぱり節目節目にハレの着物を着たわけじゃないですか。そしたら、僕らの使命はね、大きな意味で、その人の心を元気づけられるように、僕らが心底美しいと思ったものをお客様におすすめして、求めて頂く。病気にならないのだからいいじゃないですか。やっぱり、現代はまっとうなものを見て、まっとうなものを食べて、まっとうなものを纏っていないのかもしれない。高い安いを超えて、そういう考え方も大事かなと思うわけです。
■飛天錦
風合いは備前の土味で、デザインは磁器っぽい。両方の良さを融合させているこの帯の原型は、帯屋さんとのこんなやりとりでした。
勝山 : もとは洛風林さんから依頼されて織っていて、サンプルを見せるともう少し金の量を減らして欲しいと言われたんです。それで金糸の撚りを戻して…、普通に織ったら綺麗に織りあがってしまうんですが、巻いて戻してもう一回巻いて、ということをしているので巻きムラのようなものが出来ています。これは織機ならではで、手機ではこうは出来ません。偶然の産物なんですけど、技術的に難しい要求でも出来ないとは言いたくないので。
|
|||||||
|
|
| ←back・next→ |