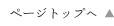対談この人と
話そう...
 |
たかす文庫「この人と話そう…」 陶芸家 鈴木 涼子 さん |
||||
| 聞き手 蓮井将宏(や和らぎたかす店主) | |||||
〝 古瀬戸 〟に訪ねて 鈴木さんはいつも「古典をしっかり学び、創作の基本としたい」と話します。 無我の心で作品を創作する女性です。師は明代の器。 テレビも見ないでオフラインで暮らし、謙虚に生きる彼女(ひと)です。 美しい物には幸福と道徳的な力があります。 ヴァルター・グロピウス(建築家)の言葉を送ります。 〝 絶対確実な技術を磨け、そして後は霊感のなすがままにまかせよ 〟 古典がお手本 蓮井:鈴木さんは立命館大学で中国文学を勉強した後、すぐ陶芸の道に? 鈴木:いえ、一度就職して、陶芸を始めたのは25くらいの時です。元々きちんと積み重ねて一生続けられる仕事がしたいと思っていました。絵を描くことが好きでしたので、何かを作る仕事に就きたいという気持ちも強くありました。25という年齢になったときに今から新しいことをするには最後のチャンスだと思い、具体的に考えを進めるうちに工芸的なものがより長く積み重ねられるのではという考えに行き着きました。色々なものを見たり体験をした中で、陶芸が一番合っていそうな気がして、地元が名古屋ですので焼物といえば瀬戸が産地だと思い、瀬戸の窯業高校の専攻科に入りました。 カリキュラムは2年間ですがその終わりごろに個人的に焼物の中でも古いものに興味がわいて、古染付の虫食いはなぜあのようになるのだろう、南宋官窯の青磁は何故あのような亀甲(貫入)がいっぱい入っているのだろうとか、そういう観点で見るようになって、その後、瀬戸市の新世紀工芸館というところに所属して設備を使わせてもらいながらそこで2年、それから独立しました。 蓮井:例えば、古染付というと明末の中国で日本向けに作られた器で、茶人に好まれるものですけど、鈴木さんはどこに魅力を感じますか? 鈴木:どこと言葉で言い切れないですけど…。民窯の創意工夫がより強くかんじられる作風はとても魅力的ですが、やはり、基本的な焼物ならではの手強さが一番の魅力です。そこには圧倒的な造形力とか…絵もそうですし、あと素材感が関係してますよね。胎や釉肌、呉須の色と雰囲気。染付はその組み合わせがすべて関わった上で焼きのこともありますので複雑です。原料、素材については日々試験してるんですけど、なかなかその手強さには近づけなくて。制作の基本は素材の試験が中心で、その間に作品を作るという感じです。同じ素材で作品を幾つも造る場合もありますけど、基本的には試験を繰り返して、その時に一番ベストだと思った原料を使って、作品にしてます。試験にはいろいろなやり方があると思うのですが私は中国現地の原料を使いません。古典を再現したいというわけではなくて、構造が知りたいという感じです。瀬戸でやってるからなるべく瀬戸の原料を使って、分析値からゼーゲル式をたてなおして現存の素材におきかえて計算して、それにより近いものを。感じを掴みたいんです。 蓮井:創造的な仕事してたら波とかないですか? 鈴木:波はあまり…、今は、土台をしっかりさせるということに集中して、自己表現というのではなく、長くずっと飽きないような良い焼き物が作れるように、古典に倣ってに基本を勉強するということを大事にしたいです。 蓮井:丁寧な仕事をしていきたいんですね。 蓮井:でも昔はそれぞれ分業でやってたじゃないですか。それをあなた一人で立ち向かっているわけですから、たいへんなことですよ。 鈴木:無謀なんですよ(笑)。でも一人でやる良さもあって。同じ作業ばかりやってると、客観視できなくなってしまう。いろんな作業があることで、客観視できるという意味では良いんだと思います。 蓮井:作家の良さってそういうところかもしれませんね。 鈴木:客観視するために気を変えるとか、目を変えるとか。その代わり技術的に一つが突出して熟していくことはできませんけど、良い感じを大きくとらえられることを大事にしたいと思っています。 蓮井:それは今聞いていてハッとしました。確かにそうですね。僕はものを作る時に一番大事なのは方向性だと思うんですよ。時代の要請に応えられないと。聞く耳持つとかね。だからいつも客観的に自分を見るって大事なことですね。 ✳︎ ✳︎ ✳︎ 蓮井:10年後の夢はなんですか? 鈴木:ずっと飽きのこない良い焼き物を作ること。何年たっても飽きないものを造るために、10年後も今と変わらず基礎試験を続けている気がします。良いものとは土台がしっかりしていて、流行に捕らわれないもの。例えばもし私の造ったものが百年後に陶片になっていて、それを見て「これが何かは分からないけど気になる、この感じはどういう構造になっているんだろう?」と思ってくれる人がいたら、縁が回っている気がしません?そうやって物に関わる大きな螺旋状のものに私も加われたらすごく嬉しいなと思っているんですけど。 |
| vol.81(2019年6月発行)より |
|
|
| ←back・next→ |