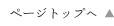対談この人と
話そう...
 |
たかす文庫「この人と話そう…」 木工家 新宮 州三 さん |
||||
| 聞き手 蓮井将宏(や和らぎたかす店主) | |||||
|
尊い時間 蓮井:新宮さんはご両親が美術に興味があって、暮らしの中に芸術があったんですよね。 どういう経路で今にたどり着いたんですか? 新宮:岡山の榎本勝彦さんの漆を中学生の時に見てて、それから漆というものがずっと頭にある状態で過ごしてきてたんですね。大学は彫刻科やったんですけど、卒業後の進路を考えた時に、漆をやってみたいと漠然と思って、すぐに輪島の漆芸技術研修所に行ってみたんですよ。それで漆をやることになったんです。 蓮井:輪島で赤木明登さんや奥さんとも出会ったわけですね。 新宮:そうです。赤木さんはやっぱりカルチャーショックやったですね。生活とか。 蓮井:まだ初期の頃ですよね。小屋が一つあったくらいの時ですかね、犬がいて、子供たちがいて。その時は赤木さんと研修所と両方かけもちだったんですね。その二か所で学んだことというのは全然違うんじゃないですか? 新宮:おっしゃる通りです。とにかく両極になる仕事を同時進行でやっていたという感じですね。 蓮井:片方は伝統工芸、片方は暮らし、作家と職人という感じですかね。その両方を学んだことが余計に良かったのかもしれませんね。 新宮:僕は最初研修所の方に行ったので、漆といえば伝統工芸展というような環境やったと思うんですけど、ただ僕は木地から塗りまでやるというのは決めてたんで、いつか木地はやろうと思ってたところに、赤木さんからバイト来へんか、と誘って頂いて。当時は赤木さんのことも全然知らなかったんですけど、漆の勉強が出来てお給料も貰えるんやったらいっか、というくらいの感じで。赤木さんのところでやらして頂いたのはひたすら数仕事で、ひたすら布を貼るとかひたすら木地固めをするとかひたすら研ぐとか、そういう下仕事です。十時からスタートで六時七時くらいまでやるんですけど、僕、手が遅いというか、迷惑かけてる、という気がしてたんで最後終わるまで残ってやってたんです。そしたらある日ね、夕暮れ時に、番頭の職人さんも帰って、僕と赤木さんと二人になって、ひたすら塗り続けてたら、ゾーンに入ったというか、忘我の状態でひたすら塗ってて…、ふって気が付いたら赤木さんと目があって、「どや、気持ちええやろ」って言ったんですよ、赤木さんが(笑)。仕事は個人個人でやってるんですけどお互いに分かり合える、というような経験があったのをよく覚えています。 ◆ ◆ ◆ 新宮:僕、輪島で自損事故を起こしたことがあるんですよ。人生で三本の指に入るくらい苦しい時に、赤木さんが手を差し伸べてくれたんです。当時赤木さんところでバイト初めて一か月くらいだったんですけど。今でもその時の事をずっと感謝してて。それからもう一人、研修所のボイラー技士さんをされていた北山さんという方、この人はもともと木地師さんで、僕、授業が終わってから二年間、この人に教えてもらっていたんですよ、無償で。この人のおかげで今自分で木地挽いたりできるようになったんですけど、この方も僕が事故の後処理で困っていた時に手を差し伸べてくれて。だからこの二人には一生かけて返していきたい、大恩があるんです。輪島を出る時に、結局何を一番感じたかというと、赤木さんがいつも冗談で言ってた、「愛だよ」っていう、その愛情をすごく感じたんですよ。 蓮井:じゃあそういうリスクを負ったけれども、輪島での日々は尊い時間だったんですね。ある人がいってたけど、リスクというのは体験なんだって。リスクがあることはいけないことだと皆思ってるけど、前向きにとらえて、誰を恨むではなく、感謝すること。リスクを負って、経験したからこそ人の気持ちがわかるんです。 厨子の時代 蓮井:輪島時代が終わってからは? 新宮:研修所は五年やったんで、五年いるという選択肢もあったんですけど、赤木さん処でアルバイトしたのが大きくて、飯を食うための仕事というのは数をしなくちゃいけないというのが頭にあって、もともと木地からやりたいということもあったんで、弟子入りをしっかりしようと思って、親方のところに。※村山明に弟子入りしました。[※重要無形文化財「木工芸」保持者(人間国宝)(一九四四–)黒田辰明氏に師事] 蓮井:村山さんのところへ行こうというのは自分で調べて? 新宮:そうです。当時、刳りものをやっている人が少なかったですし。僕は刳りものがやりかったので。 蓮井:村山さんのところでは七年半、その間にも色々な人で出会っているそうですが、最近思うことは何かありますか? 新宮:思うことと言いますか、以前に蓮井さんに「厨子を作ってほしい」とメール頂いたんですけど覚えてはります?僕もずっと厨子作りたいと思ってたところに頂いたメールだったんで、でもむちゃくちゃ難しいんですよ。ただ、こういう時期でもあるんで、余計に厨子というものの意味合いも出てくる気がしてて。でもそういうのを言うてたら今の僕の状態では作れへんなと思ったんで。親方のところでやっていた厨子はさしものだったんですね、八角堂みたいなやつ。僕は刳りもので、彫刻的な厨子を作ろうかなと思ってます。一応、六月の個展のときに…。 蓮井:それは楽しみです。昔は厨子と言い、今は仏壇ですけど、住宅事情も色々ある中でね、目に見えないものに対しての感謝ってなくなっていっている気がしません?だから物も大事にしない。でも僕はこれからは物を大事にして生かすという時代にしないといけないと思っているんです。物を作る人たちはそのために物を創ってるんであって。混沌とした時代にこそ、芸術が生まれるんです。人間というのはそういう時に何かエネルギーが集まって、浄土を作ろうとする。今を浄土にするという想いが大切ですね。今日がなければ、明日はない。そのために一人一人仕事があって、みんなで協力していく。今は厨子の時代、祈る時代。自分の心を静寂にする、そういう場所を作らないと。自分というものをしっかりもってぶれないようにするために〝 暮らし 〟があるんだと僕は思います。 新宮:厨子に取り組むときの心構えが今出来ましたね。 |
| vol.85(2020年6月発行)より |
| ←back・next→ |