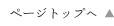対談この人と
話そう...
| たかすのきものめぐり③ | 織物作家 柳 崇さん |
||||
| ■いい裂をつくる織物屋でいたい 柳崇さんは「民芸運動」の創始者、柳宗悦さんを叔父にもち、昭和29年に工芸の世界の頂点である柳一族に生まれ落ちた人です。自身は織り人として、東京の一画に自宅兼工房を構えて、静かに日々の仕事をしています。 その工房を訪ねたのは6月のはじめ、新緑が力強い緑に変わる頃でした。60年を経た巨木と呼ぶにふさわしい2本の桜に守られるようにしてあるその工房の入り口には「柳舎」という青銅の銘版が掛かり、その銘版に木漏れ日がさまざまな陰影を映し出していました。風がよく通る工房には織機が3台。1台は柳さんの、1台は奥様の、そしてもう1台がお弟子さんの機です。その3台の機を傍らに、小さな中国の椅子に腰掛けて、柳さんの機織りに対するいろいろな思いをお話いただいたのでした。 「僕は織物屋でいたいと思っていましてね。つまりいい裂を作りたいんですよ」 柳さんは言います。柳さんにとっての「いい裂」とは「日本の風土で育った良質の繭を座繰りでゆっくり引いて作った穏やかな糸を使って織った、やさしい厚みのある生地のこと」を指します。どの段階においても無理していない、いじめていない。そんな糸、そんな織物が自分の追い求めるものなのだと。 そうしてできたやさしい風合いの生成り糸とニュアンスのある色糸を絡ませながら、柳さんは帯を織り進めます。よく見ると、柳さんが染める糸色は、萌黄や茶色、山吹色など窓から見える庭の草木の色にそっくりです。庭の土と草木の様子がそのまま機の上にあるように、帯が機にかかっているのです。 「日本にはいろいろな織物技法がありますが、僕は柄に逃げることを避けるようにしています。織物の生命は生地だと思っているものですから」 と柳さんは言います。素材のよさと基本の確かさ。それが柳さんの身上であり、柳さんの織物の魅力です。 |
| ■いつも周りに本物があった とはいうものの、柳さんは難しい人生を歩んだり、織物についてストイックな勉強をしてきた人ではありません。大学の経済学部を卒業し、そのまま何となく織物を始めたという「らしからぬ人」です。お父様も高名な織物作家でしたが「考え方も技術も何も教えない、言動の束縛もしない。実におおらかで和やかな人だった」そうで「父から薫陶を受けたなんて記憶はない」のだそうです。 「でも感謝しているのは、柳の家に生まれたことでいつも本物が周囲にあったこと。大学生のときのアルバイトは民芸館の陳列の手伝いだったし、父の用で付いていった先は芹沢銈介先生のお宅だったし、小さいときから知っていたちょっと変わったおばちゃんは白洲正子さんでした。だから意識せずに本物を見てきたし、本物に触ってきたんですね。こうした本物の記憶が僕の師匠になり、ものづくりのよりどころになったんです」 |
| ■品性の織物に惹かれて 柳さんの織物が大好きでこの工房に会いに来て、お願いしてうちの店で扱わせていただくようになって数年経ちます。 「なぜこんなに柳さんの織物が好きなんだろう?」と思うことが、よくあります。 今日、改めて桜の巨木に守られる工房を訪ね、菖蒲の咲く庭を見ながらお話を聞くうちに、その疑問が解けたような気がしました。それは単純な言葉で表せるものではないのですが、敢えていうならば、私は柳さんと彼の創る作品のもつ「品性」が好きなのです。その品性を、皆様と一緒に味わいたくて「僕の織物はあまり数ができないんです」という柳さんに無理を言って分けていただいて、お店で扱わせていただいているのです。 今回の訪問でもまた無理を言い、秋に新作を届けていただく約束を交わしました。皆様には、そのときに実際に〝本物〟を見ていただき、触れていただき、私がこの訪問で感じ、お伝えしたかったことを体感していただけたら、どんなにうれしいでしょう。 |
| vol.26(2005年9月発行)より |
|
|
| ←back・next→ |