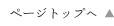対談この人と
話そう...
| 2023年3月発行(vol.96) |
 |
たかす文庫「この人と話そう…」 塗りもの師 赤木 明登さん |
||||
| 聞き手 蓮井将宏(や和らぎたかす店主) | |||||
|
岡山県金光町出身。東京で「家庭画報」の編集者をつとめているときに
塗芸の大家角偉三郎氏の作品に感銘を受け、26歳で輪島に移住し塗りの修行を始める。 32歳で独立。生活に根ざした温かな風合いの作品が注目を浴びている。 |
|
赤木明登さんと最初に会ったのは20年以上前のこと。
以来、それぞれの道を懸命に歩んできた年月を振り返りながら、岡山で個展中の赤木さんを訪ねました。 2003年にお話を伺った時のテーマは「恢復」でしたが、今回は「即如」(柳宗悦氏が用いた言葉)。赤木さんとのお話はいつも不思議と哲学が話題となります。器の奥底にひそむ心のあり様が問われているようです。「神人共食」、現代から過去に想いを馳せ、そこから暮らしの原点を考える時です。今を深く生きる事が未来を創ります。 3月の個展にて、赤木さんの器を両手でゆっくり包み込んでみて下さい。 2003年「この人と話そう」インタビュー |
|
蓮井:赤木さんと出会って22年くらいになります。3月の個展で9回目、感慨深いですね。赤木さんが能登に移り住んで何年になるんですか?
赤木:1988年からだから、34年ですね。
蓮井:今は伝統工芸の世界では人手不足と聞くけれど、赤木さんのところはいつもお弟子さんがいますよね。
赤木:ありがたいことに、そうですね。もっと増やしたいんですけど弟子入りを希望する人が少ない。来年女性が2人入ってきますが、男性は減りましたね。
蓮井:それでも、ものを作るひとを育ててきたのが赤木さんのすごいところです。
赤木:それしか出来ないですから、恩返しは。
蓮井:循環ですね。でも今までの時代と違う時代が来ています。激変する時代、赤木さんはどう思っていますか。
赤木:とりあえず、僕みたいな規模で、比較的手の届く値段で漆の器を作ってみなさんに使ってもらおうとたくさん提供する時代は終わりますよね。まず漆の分業制を担う職人さんがいなくなる。それから材料がなくなる。漆自体、国産は1%くらいです。
蓮井:クライアントもいなくなりますよね。
赤木:これまでの日本は中間層が豊かで、そういう人たちが着物や漆を使ってくれていた、その層がごそっと抜け落ちてしまいました。後は漆の木を植えるなり、作家の作品として少量制作されたものがわずかに続いていくんだと思います。ですから今、僕らができることは、ものの精神性をまだその物があるうちに伝えていくことだと思います。
|
|
蓮井:漆の器の精神性とは?
赤木:それはもう、ありがとうの気持ちじゃないですか。輪島塗のお椀というのはただ食べ物を中に入れて食事をするための便利な道具ではなくて、神様と人が一緒に食事をするための道具なんですよ。高台の高いお椀というのは何のために作られたものかというと、両手でささげ持って神様にお供えするため。特に漆椀というのはそうですよね。神様に主食であるご飯をお供えした後、下げて人間がいただきますといってご飯を食べるのが基本。
蓮井:神人共食ということですか。
赤木:そうです。神様と一緒に食べて神様のパワーをもらうということが日本人の食事の本来の起源ですから、それを伝えるというか、掘りおこすことが日本人の暮らしにとって重要じゃないかと思います。僕の作るものは基本的に昔のものの写しですけど、形だけを写すのはただの形骸化で、やっぱりどうしてこういう形になったのかという心の方の問題をちゃんと自覚して伝えていくというのがこういう器を作っている人の仕事ではないかと考えています。
例えば、これと同じコンセプトのお料理屋さんがあるんですけど神様と一緒に食事をするということを隠しテーマにして、そこでは高級食材は何もなくて、今この瞬間にその土地で採れたものしか出てこないんです。何故ならこの瞬間、この土地で採れたものにしか神様はいないですから。それを遠くへ持って行っても、そこにはもう神様はいない。
蓮井:神様というのは生命力?
赤木:神様というのは…、自然そのもの、何か根源的なものですよね。でもそういうものがあるかどうかはわからないけれど、重要なのは、そういうものがあると仮定して時間を過ごす僕らの心持ちのほうなんです。その心持ちというか心のあり様を器に表すということが僕にとって作るということなんです。
民藝運動を主唱した柳宗悦は若い頃は宗教学者、キリスト教の研究から始めて、道教、仏教に進んでいくんですけど、その三つの宗教のそれぞれの土台になっている共通のものを見つけ出すんです。それが柳の言い方だと「即如」。即はすなわち、そのまんまですよね。如は如し、で、具体的には何も語っていないんですけど、仏教でいうと無、空、不二、道教では道、キリスト教ではgod as he is、これらを訳したものが「即如」。有に対立する無ではなくって、有でもない無でもない、なにもない状態…。全てはありのままで満ち足りていて完璧であり、言葉でこれを定義しようとすると人為的になるので暗示させるしかない、その「即如」という全ての宗教の土台になるものを柳は発見して、その土台に基づいた心のあり様があって、その心のあり様が表れているのが民藝だと言っているんです。
蓮井:手でも葉っぱでも食べられるけど、器を使うということは、古来の日本人はそういう気持ちで作って使っていたんですね。
赤木:纏うこと、食べるということもそれと同じです。食材の中にはそのものが育った山、大地、海、空の記憶があって、それに触れることが出来れば、そこに神様がいて、人間の心が震えるんです。漆で言うと、漆は本当に天然の賜物で、自然の中にあるときは完璧な存在で、その完璧さを僕らは塗る時に取りこぼしてしまうんですよね。できるだけ手を加えずに、漆の持っている完璧さを引き出す、それが出来れば十分だと僕は思っています。
蓮井:その為には技術が必要なんですね。着物もそうです。織物で一番難しいのは平織。シンプルなものが一番難しいんです。
赤木:でもそこに深い世界があって、狭い幅の中に奥行きがある。追求するとキリがないですけど、それが自然の面白さです。その先には言葉にできない世界があって、その世界こそ、神様がいる世界で、ありがとうございますと手を合わせるしかないですよね。
|
|
|
| ←back・next→ |